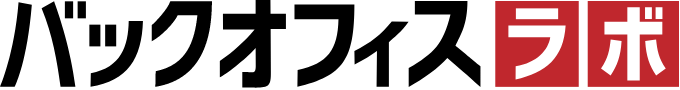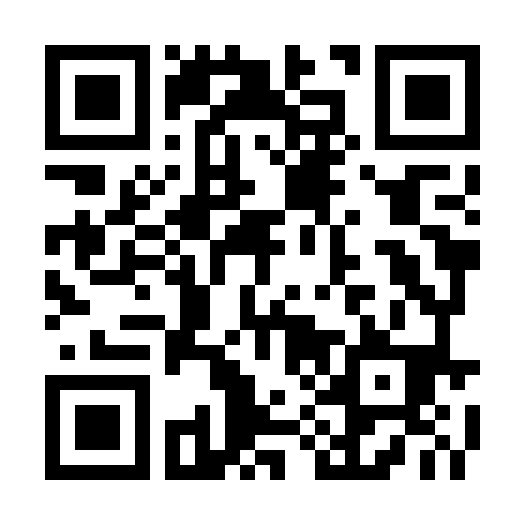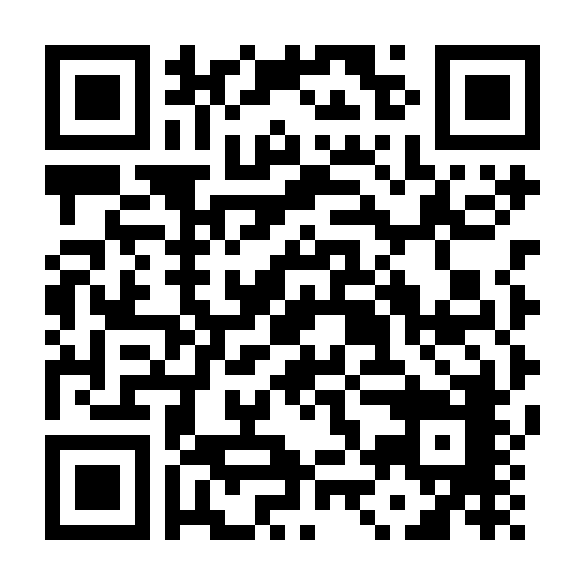5Sの目的・メリットとは?取り組む前の準備や各ステップのポイント、事例も解説
2023年11月28日 06:00
この記事に書いてあること
5Sに取り組んではみたものの、効果が感じられないと悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。この記事では、5Sとは何なのか、取り入れる目的やメリット、取り組む際の手順や注意点などについて解説していきます。
5Sの定義・対象とは
はじめに、5Sの定義や対象を解説していきます。
5Sの定義
「5S」とは、「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「躾」の頭文字をとってつくられた言葉です。具体的には次のようなことを指します。

1. 整理(Seiri)
整理は「必要なものと必要でないものを仕分けし、不用品を処分すること」を意味します。
2. 整頓(Seiton)
整頓は「必要なものを使いやすいように並べること」を意味します。
3. 清掃(Seisou)
清掃は「身の回りを掃除しつつ点検すること」を意味します。
4. 清潔(Seiketsu)
清潔は「整理・整頓・清掃された状態を保つこと」を意味します。
5. 躾(しつけ)(Sitsuke)
躾は「ルールや基準を守り整理・整頓・清掃するように習慣づけること」を意味します。
5Sは難しいことではありません。当たり前におこなわれることですが、5Sを意識・徹底することにより職場環境の改善が見込めます。
5Sを取り組む対象
5Sの対象としては、4M、1Iが挙げられます。
4M
4Mは、モノ(Material)、設備(Machine)、作業方法(Method)、人(Man)をまとめた言葉です。ついモノや設備に意識が向いてしまいますが、人や作業方法も対象になります。
「人」に関しては、「躾」にも通じますが5Sに対する意識やルールを守ってもらえるような働きかけが、「作業方法」に関しては、業務そのものの整理整頓やマニュアルの作成が挙げられます。
1I
5Sは、1Iも対象になります。1Iとは、情報(Information)のこと。業務で使用するパソコン内のデータの整理整頓や顧客情報などが対象になります。
5Sを取り入れる4つの目的
5Sを取り入れる目的は、大きく分けて4つあります。それぞれどのような目的なのか、具体的にみていきましょう。
1. 無駄をなくし作業効率を上げる
5Sを徹底し、整理整頓や清掃がしっかりと行われている環境をつくると、何がどこにあるのかが明確になり、「探す」という無駄な時間を削れます。そのため、自分がやるべき作業だけに集中することができ、スピーディーで質の高い仕事ができます。
2. 社員が働きやすい環境をつくる
5Sを意識することで、社員にとって働きやすい環境をつくれます。整理整頓が行き届いていることで、モノを探し回ったり無理な姿勢で作業したりする必要がないため、肉体的負担の少ない職場になります。また、清潔な状態を保つことで、心理的な負担も軽減できます。5Sを意識して行うことで、自主性も向上し、仕事に対するモチベーションを保ちやすくなるでしょう。
3. 安全性を高める
安全な職場環境をつくることも、5Sの大きな目的の1つです。整理整頓や清掃が行き届いていないと作業や移動がしにくくなり、事故が起こる可能性が高まります。5Sで作業しやすい環境をつくれば、安全に仕事ができます。
4. 一人ひとりがルールを守って動ける風土をつくる
5Sの徹底によって、一人ひとりの意識を改革できます。自然と自分のやるべきことを行えるようになり、ルールを守って行動できます。会社全体の風土が変わっていくため、無意識のうちにルールを守れるようになります。
5Sの定着でもたらされるメリット
5Sが定着することでもたらされるメリットはさまざまです。具体的なメリットについてひとつずつ紹介します。
1. コストを削減できる
業務効率が上がることによって残業が少なくなったり、余計な人材を雇わずに済んだりできるため、人件費を削減できます。また、徹底した在庫管理をすることで、不必要な物品購入や余計な出費を抑えることも可能です。
2. 商品やサービスの質が良くなる
ルールを徹底することで、業務中のミスや作業の品質低下のリスクを減らせます。また、余計な作業が省かれることで集中力も高まるため、商品やサービスの質が上がり、安定した品質が保てるようになっていくでしょう。それにより顧客満足度も高まります。
5Sに取り組むときの2つの注意点
続いて、5Sに取り組むときの注意点を2つ解説していきます。
1. 社内に確実に浸透させる工夫をする
5Sには社員全員の力が必要になります。そのため、社内に5Sを確実に浸透させるための工夫をしましょう。
具体的には、研修会を開く、整理整頓などをする5Sの日を決めるなどの対策が挙げられます。従業員の自主性を尊重することも大切です。命令や指示ではなく、話し合いをしながら、5Sの浸透を進めていきましょう。
2. 改善を繰り返す
改善を繰り返すことも重要です。5Sに関しては、そのときの業務内容や従業員の個性によってアプローチが変わります。そのため、固定の方法を見出すのではなく、状況に合わせて改善を繰り返していくといいでしょう。
5Sに取り組む前にやるべきこととは
5Sに取り組む前にやるべきことがいくつかあります。事前にどのようなことをすればいいのか、具体的な内容を紹介します。
5Sのレベルを把握してから計画を立てる
まずは、現状で5Sがどのくらいできているのかを把握することが大切です。改善ポイントや課題を見つけて、目的を明確にした上で計画を立てるようにしましょう。目的がはっきりすることで、より具体的な計画が立てられます。
5Sを伝える担当をつくる
5Sを行う場合には、リーダーを指名することが多いでしょう。しかし、リーダーに丸投げするのではなく、しっかりと教育することも重要です。そのため、5Sについてリーダーに正確に伝えられる担当者が必要です。
5Sの各手順におけるポイントとは
5Sを行う際には、手順をきちんと把握しましょう。
5Sは基本的に、3Sと2Sに分けて考えます。3Sは整理・整頓・清掃の3つで、5S活動の基礎となる部分です。まずは、3Sを徹底的に続けていくことから始めましょう。3Sを継続して行うことによって、清潔・躾の2Sは自然とついてきます。
整理(Seiri)
整理をする際に、ただの掃除になってはいけません。不要なモノを捨てるだけでは、また同じように無駄なモノが増えてしまいます。不要なモノを増やさないためには、何が必要なのかを明確にして、捨てる基準やルールを決めることが大切です。
「頻繁に使うことのない備品や文房具はなるべく共有する」のように、あらかじめルールが決められていると、不用品が増えずに整理された状態を維持できるでしょう。
整頓(Seiton)
整頓では、モノをただきれいに並べるのではなく、仕事がスムーズに進むように並べることが大切です。誰でも見つけやすい、取り出しやすい置き方を意識しましょう。置く場所・置くモノ・置く量をしっかりと定めて、分かりやすいように名前を付けたり、色分けしておいたりすると、誰でも使いやすくなります。
清掃(Seisou)
整理整頓が済んだあとの清掃では、どのくらいきれいな状態にするのか、誰が掃除をするのかといった基準やルールを統一しましょう。
どの程度をきれいと思うかは人によって変わるため、基準を決めておかないと揉める原因になります。そのため、チェックシートをつくり、清掃の基準を明確にすることがポイントです。基準に沿ってこまめな清掃をおこなえば、きれいな状態を維持しやすくなります。
清潔(Seiketsu)
3Sが実行できても、その状態を維持できなければ、再び元の状態に戻ってしまいます。整理・整頓・掃除が常になされている状態をつくり、人が変わった場合でも維持できるようにしましょう。3Sを継続していくためには、ルールが守られているかどうかのチェックが必要です。定期的に点検・改善して、3Sを標準化させていくことで清潔な状態が保てます。
躾(Sitsuke)
躾(しつけ)というと、命令や教育などを思い浮かべる人も多いかもしれません。しかし、5Sにおいての躾は違います。習慣化するためには、5S活動を強制するのではなく、社員が自主的に実践できる環境をつくることが重要です。全員で計画を立てて、ルールや基準を決めることを意識しましょう。
5Sの2つの事例
最後に、5Sの2つの事例を紹介します。
1. 株式会社喜多村
株式会社喜多村は、公式サイトにて製造部で実施した5S活動の事例を紹介しています。2022年6月に行われた「第3工場掃除道具置き場の改善」ではキャッチャーやフックを利用し、掃除道具を整理。ほかにも、パンチング作業シートや梱包用具置き場の設置など、業務を効率的に遂行するための5S活動に取り組んでいます。
2. 株式会社クリエイション
株式会社クリエイションは、公式サイトにて5S活動の事例・実績を紹介しています。捨てる際の基準は「例外を除き1年以上使っていないもの」とし、整理整頓を実施。社内への浸透を図るために研修を実施し、意識を高めています。社内に限らず、専門学校での研修も行うなど、幅広く5S活動を広げています。
まとめ
5Sの取り組みを行うことで、業務効率や生産性が上がったり、安全性が高まったりと、経営的にもさまざまなメリットがあります。しかし、目的をはっきりさせずに始めても上手くいきません。5Sを取り入れる目的を明確にする、ルールや基準を全員で決めるといったことを意識することが大切です。
社員が自主的に取り組むようになれば、5Sも習慣化していきます。職場内の5Sを習慣化させることで、社員全員が働きやすいと感じられる環境を実現しましょう。
右のフォームからお申し込みをお願いします。
お役立ち資料ダウンロードのリンクを記載したメールを返信いたします。
記事タイトルとURLをコピーしました!