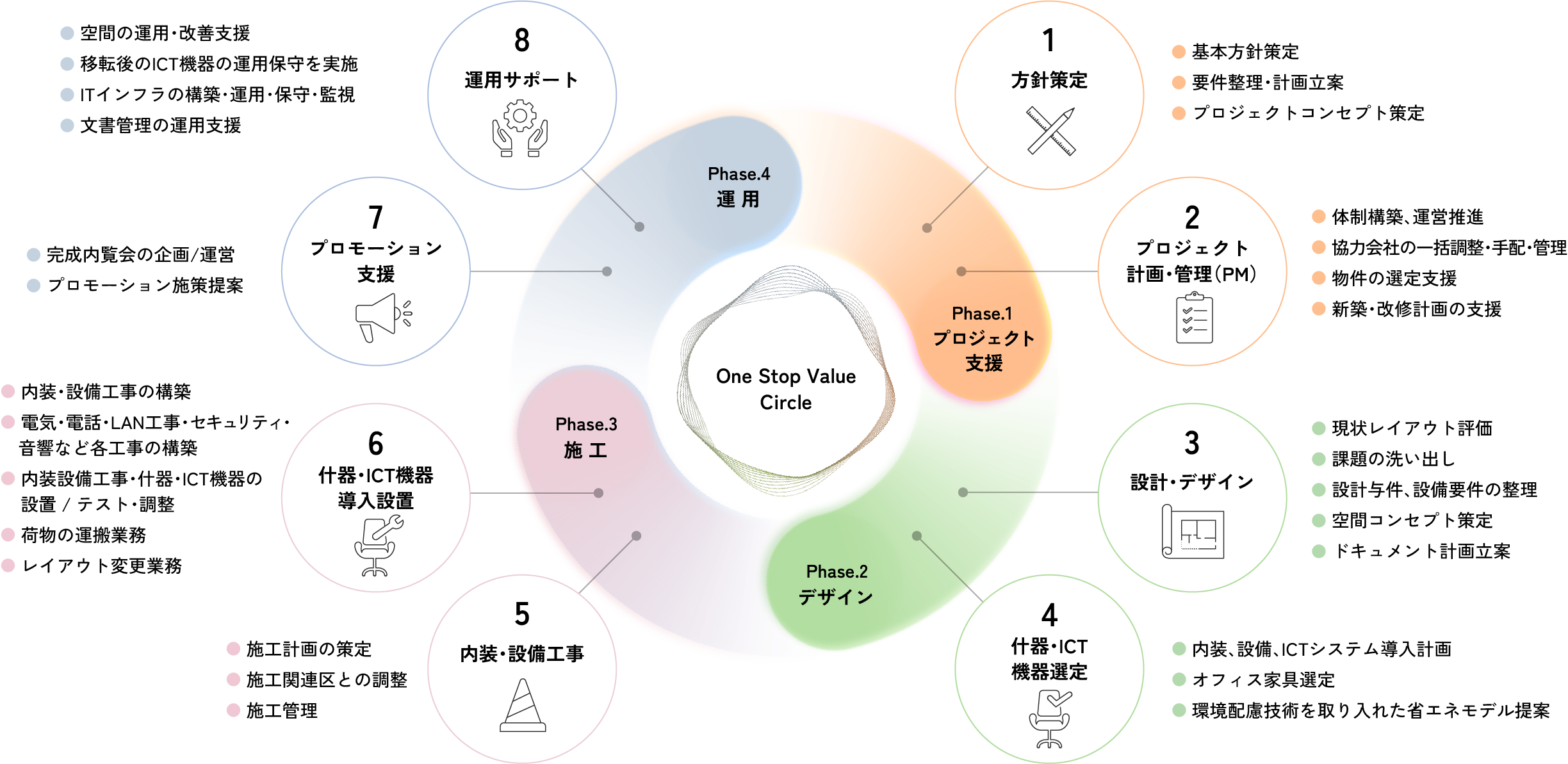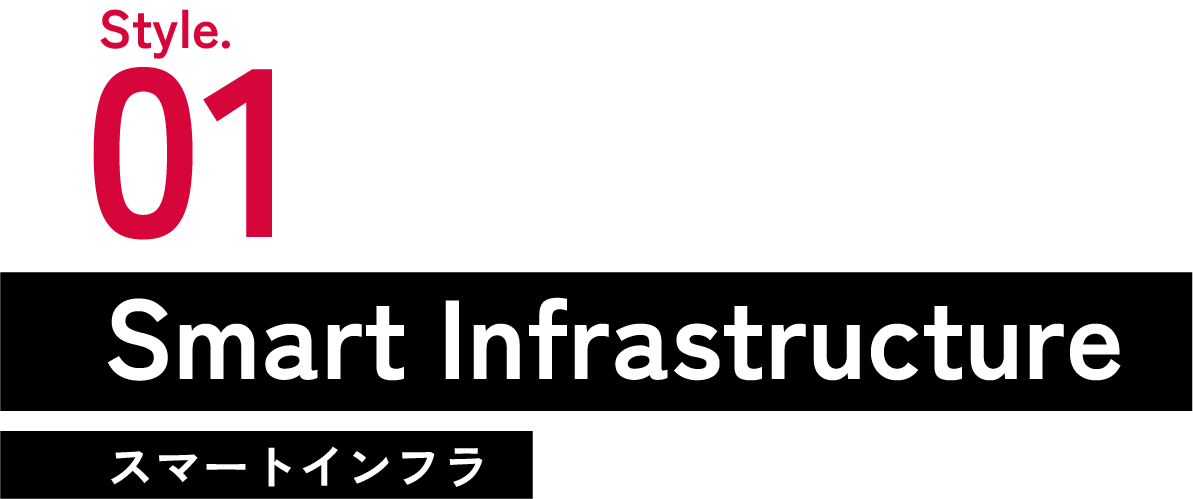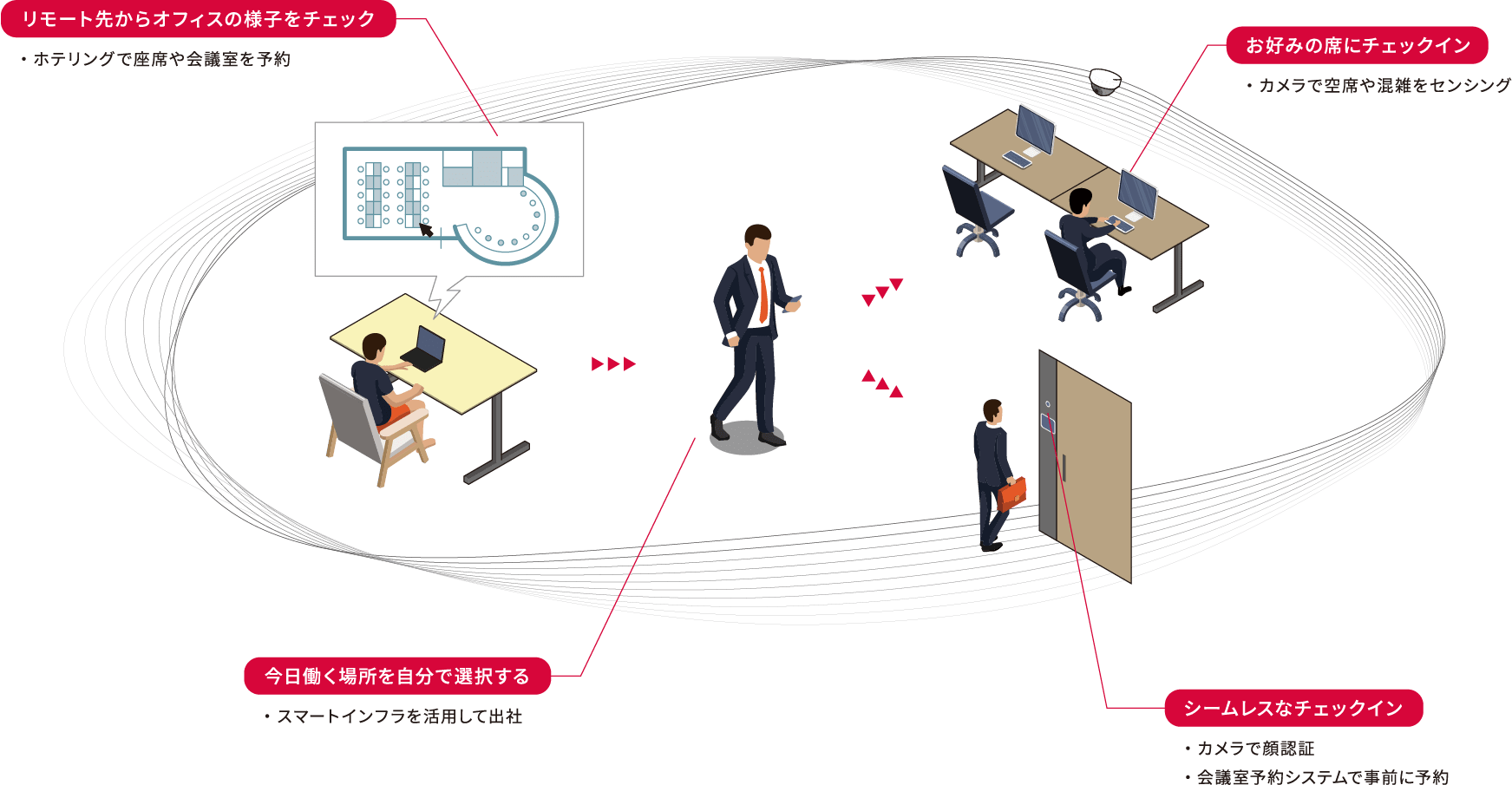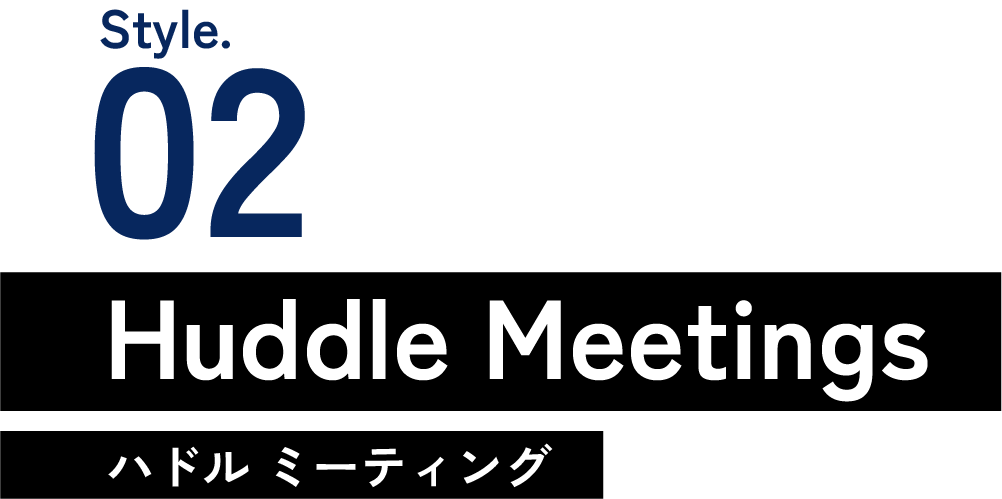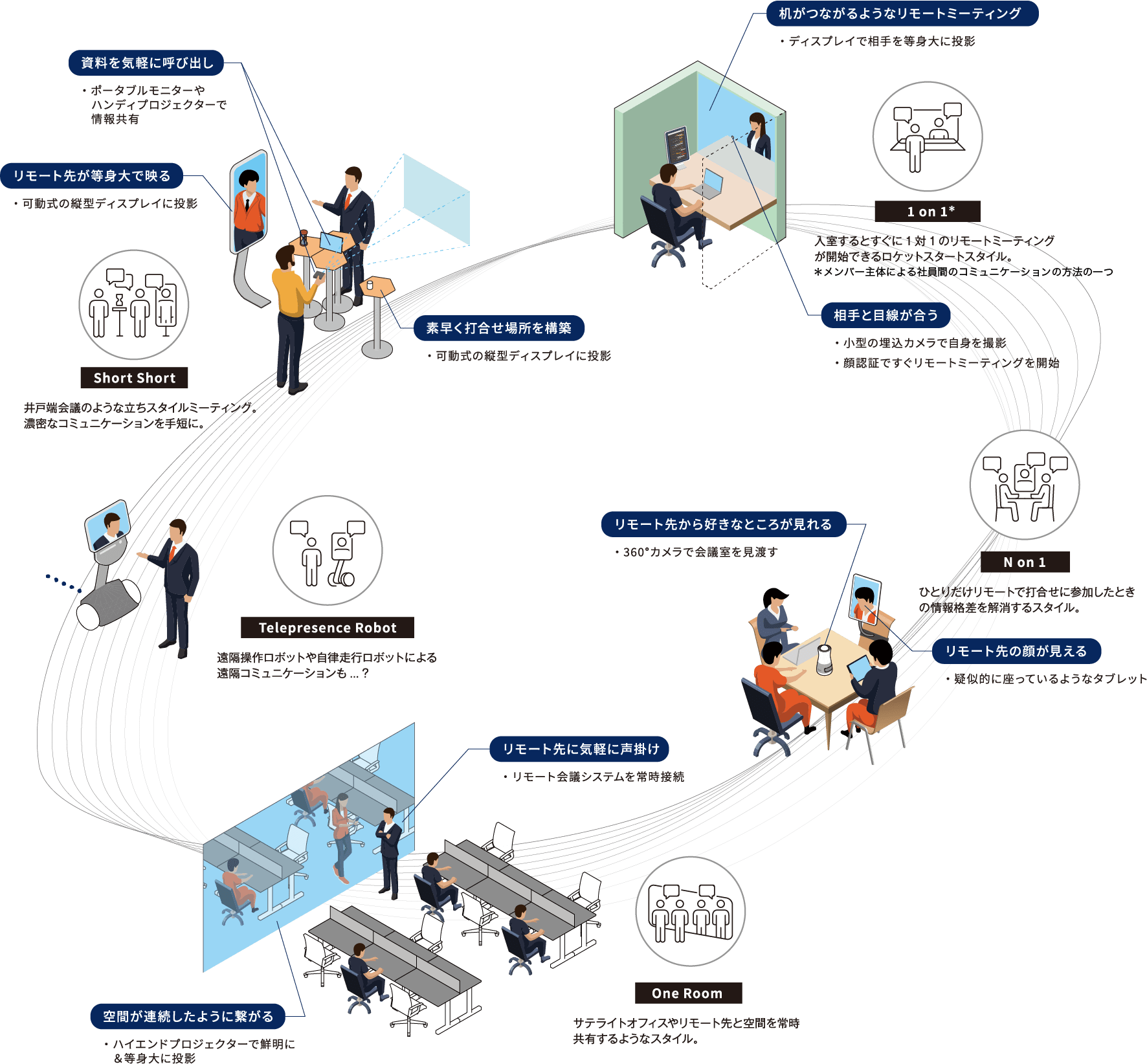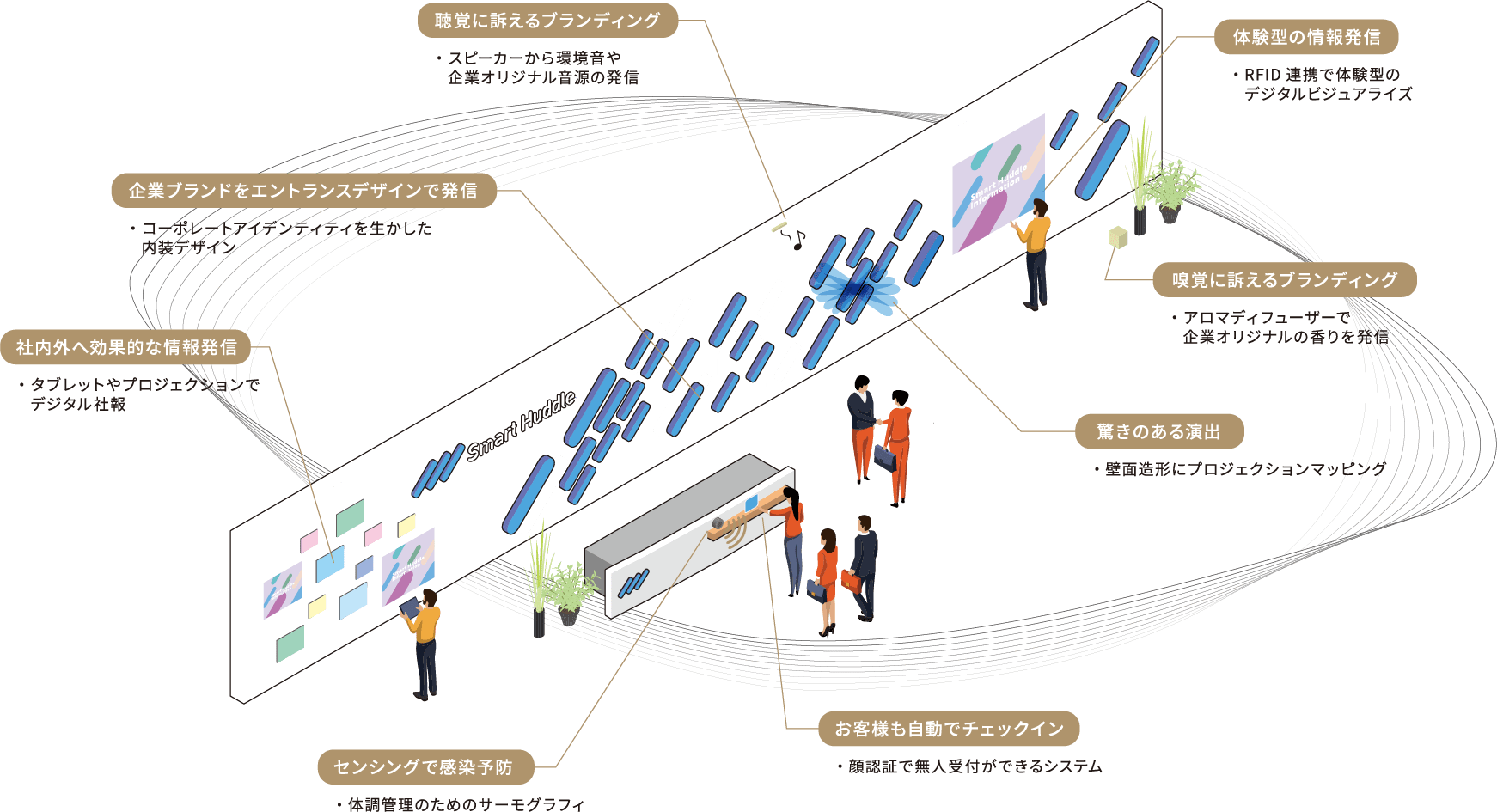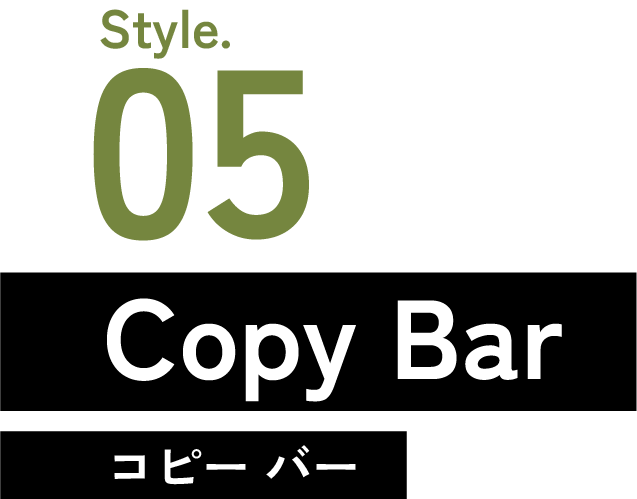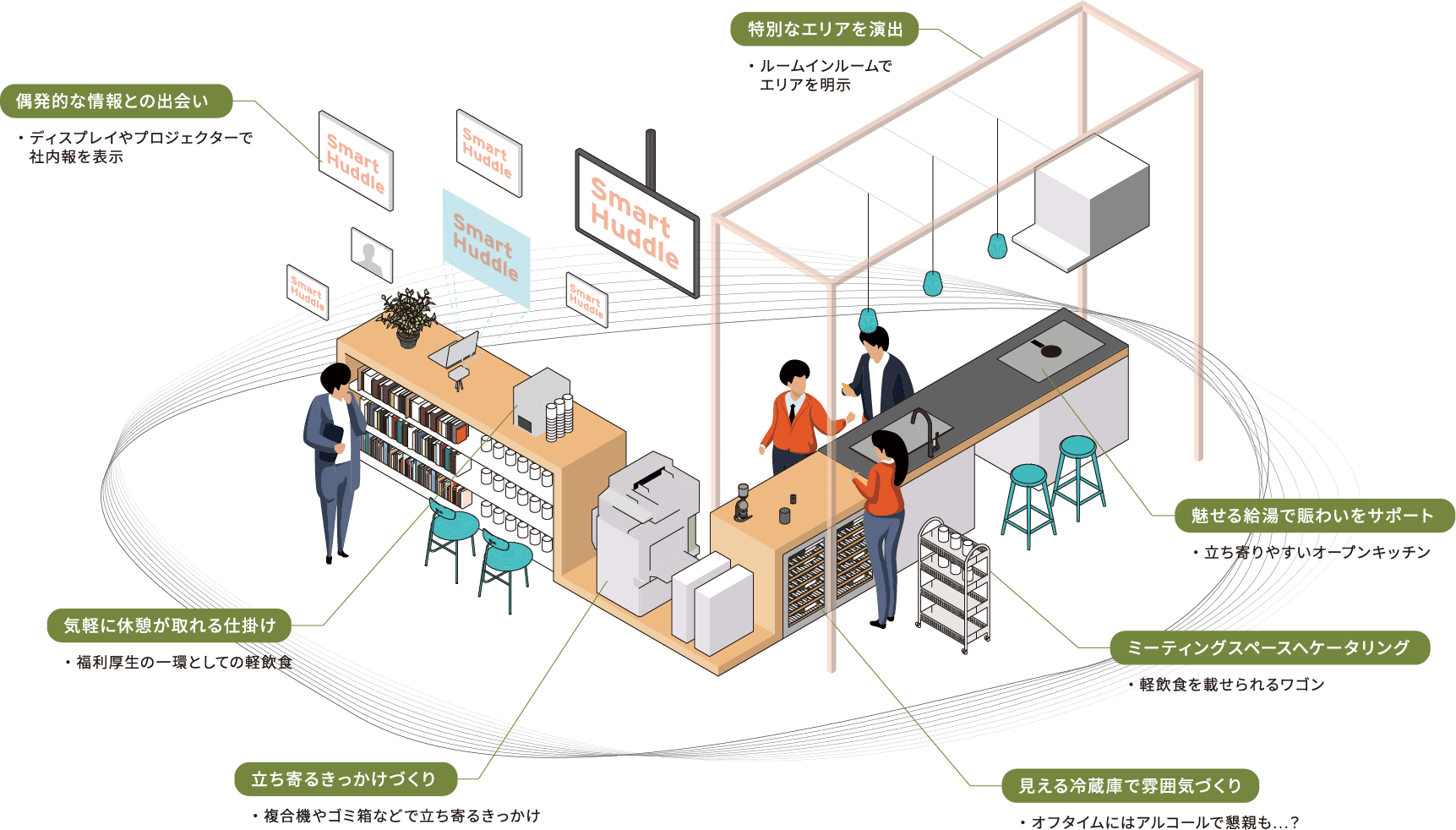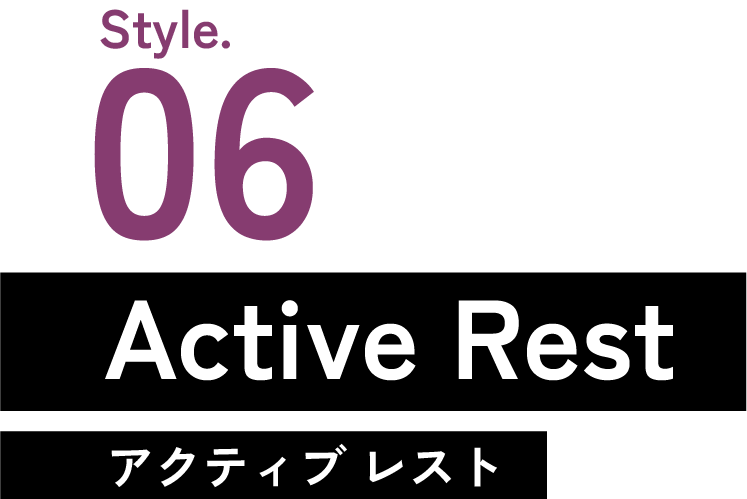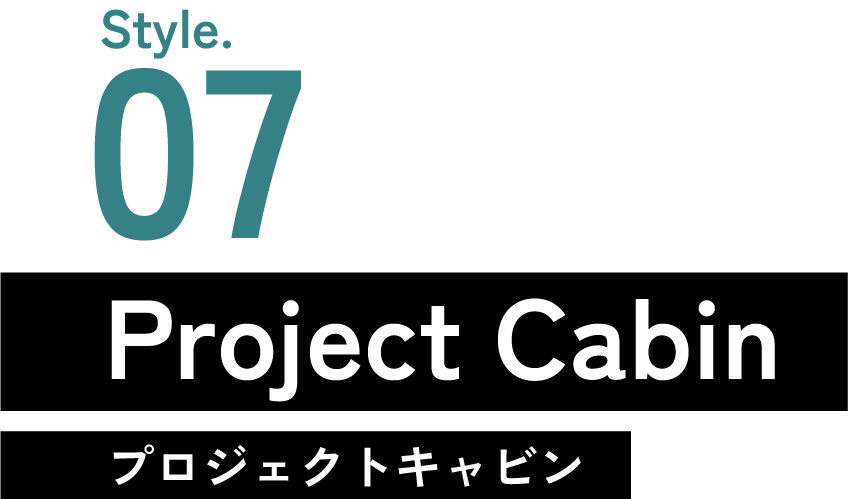それは好きな時に、好きな場所で、
自由にはたらける
ワークスタイルのコンセプト。
はたらき方のスタイルから、これからのオフィスを考えます。
-
リモートワークの普及により
失われつつあった
社員同士のつながり
-
社内文化や
理念の継承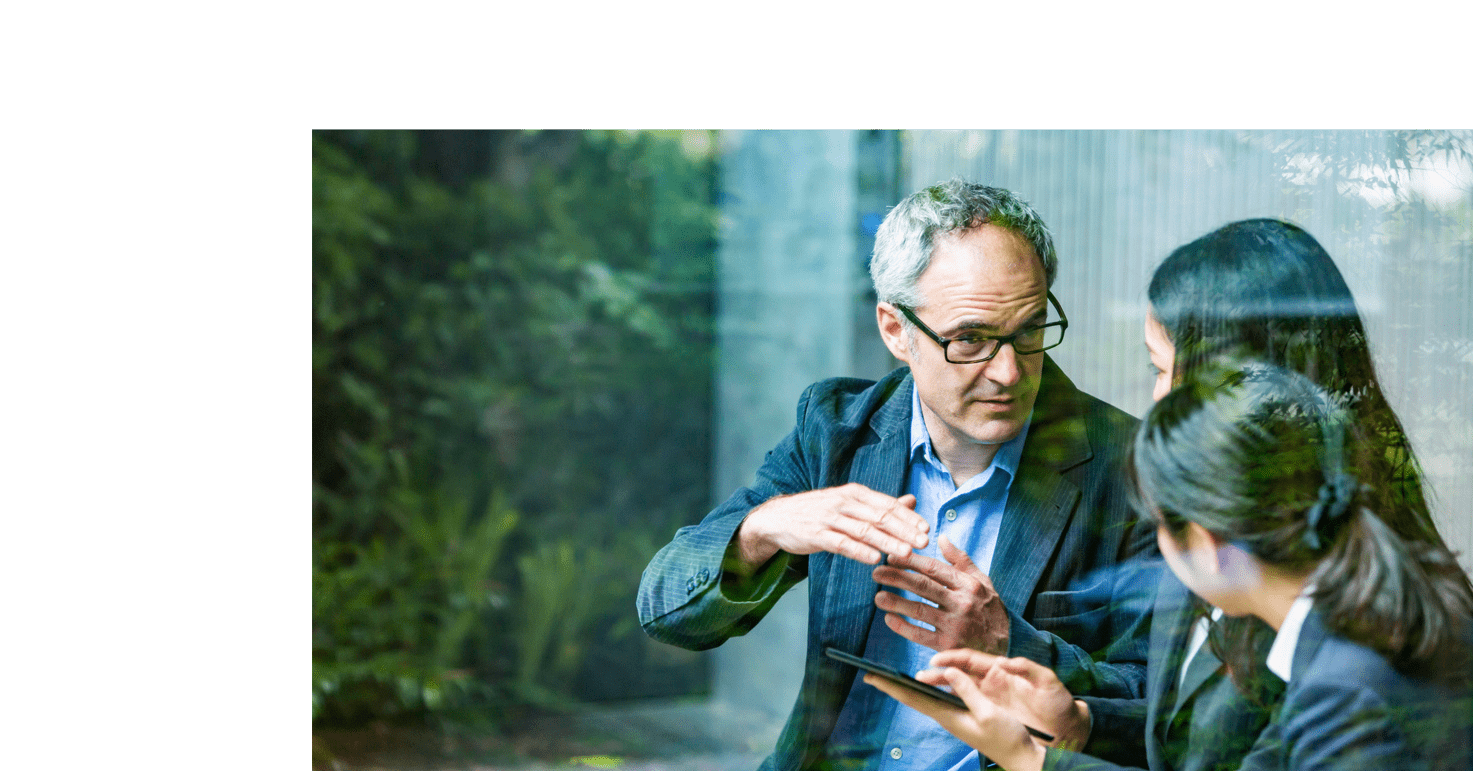
-
フェイストゥフェイスによる
生産性や創造性の
高いコミュニケーション
はたらき方のスタイルから、これからのオフィスを考えます。
-
リモートワークの普及により
失われつつあった
社員同士のつながり
-
社内文化や
理念の継承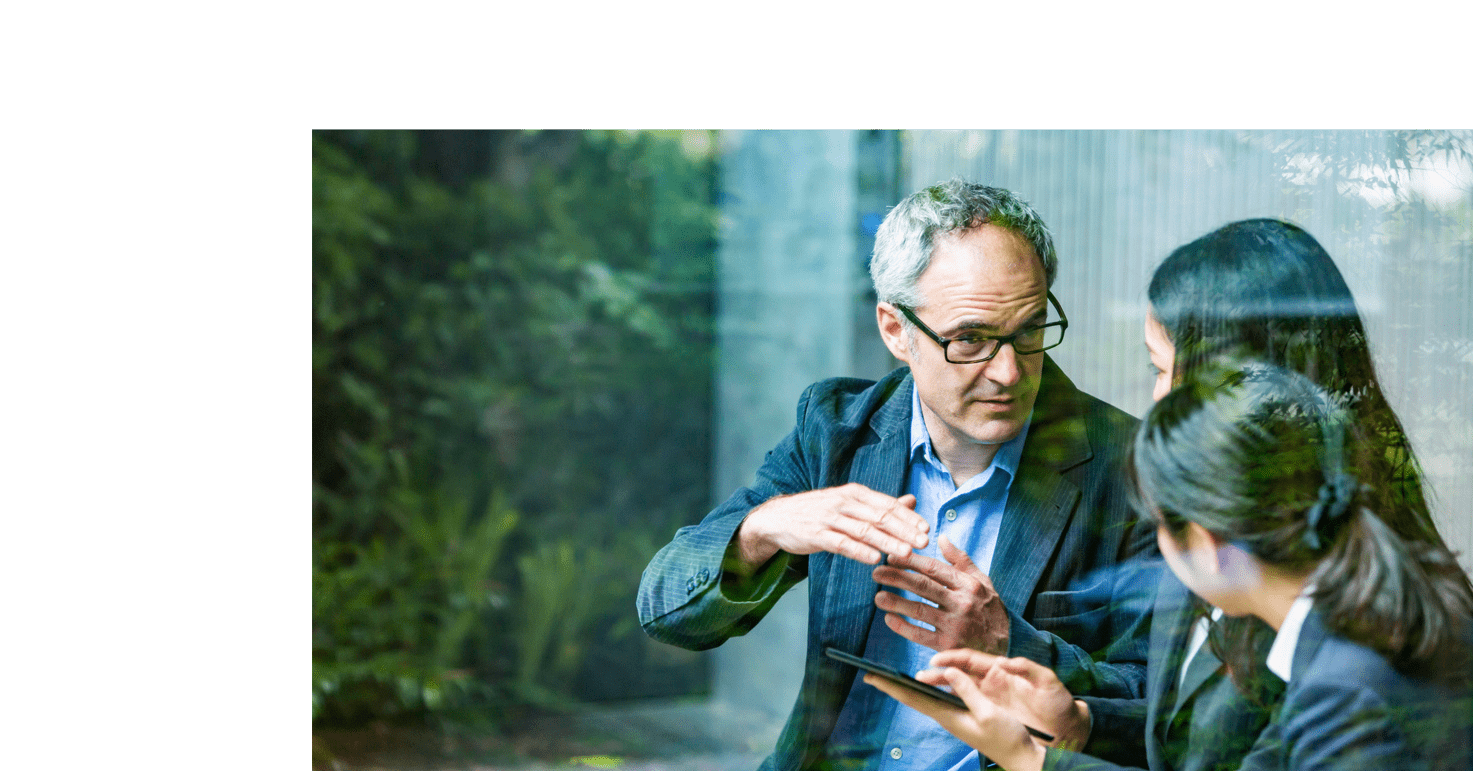
-
フェイストゥフェイスによる
生産性や創造性の
高いコミュニケーション
オフィスの価値を創造する、
リコーからの提案です。
デジタルサービスとワークプレイスデザインの
両輪で最適化してゆく。それがリコーの強み。

7つのワークプレイススタイルのご提案
7つのワークプレイススタイルのご提案
RICOH Smart Huddleのワークプレイスを360°ビューで体感できます
※RICOH Smart Huddleのワークプレイスを360°ビューで体感する内容はイメージです。LiveOffice「ViCreA」
ViCreA
とはValue innovation Creative Area
私達のワークスタイル変革へのチャレンジを、お客様にご体感していただく空間、「LiveOffice」です。
ViCreAでは、社内実践事例のご紹介を通して、お客様の価値創造へのお役立ちをさせていただきます。自ら実践した内容だからこそ、成功事例はもちろんのこと、失敗談も含めた、生のノウハウを、お客様に自信を持ってご提供する事ができると考えております。
移転・リニューアルについてのご相談、ViCreA⾒学など、RICOH Smart Huddle全般についてお気軽にお問い合わせください。
リコーグループのリソースで
移転・リニューアルをワンストップでサポート。