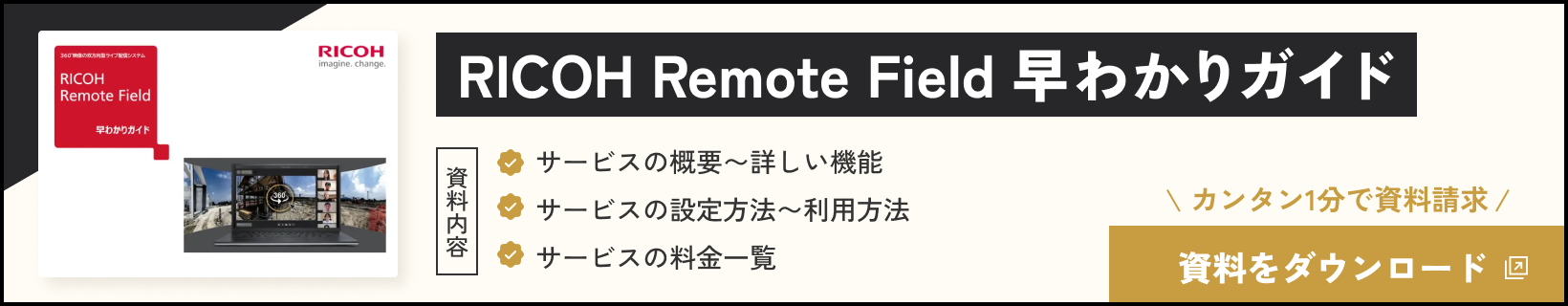- ホーム
- RICOH Remote Field
- お役立ち記事一覧
- 【初心者必見】遠隔臨場とは?国土交通省が推進する理由やメリット、注意点、活用事例をご紹介!
【初心者必見】遠隔臨場とは?国土交通省が推進する理由やメリット、注意点、活用事例をご紹介!
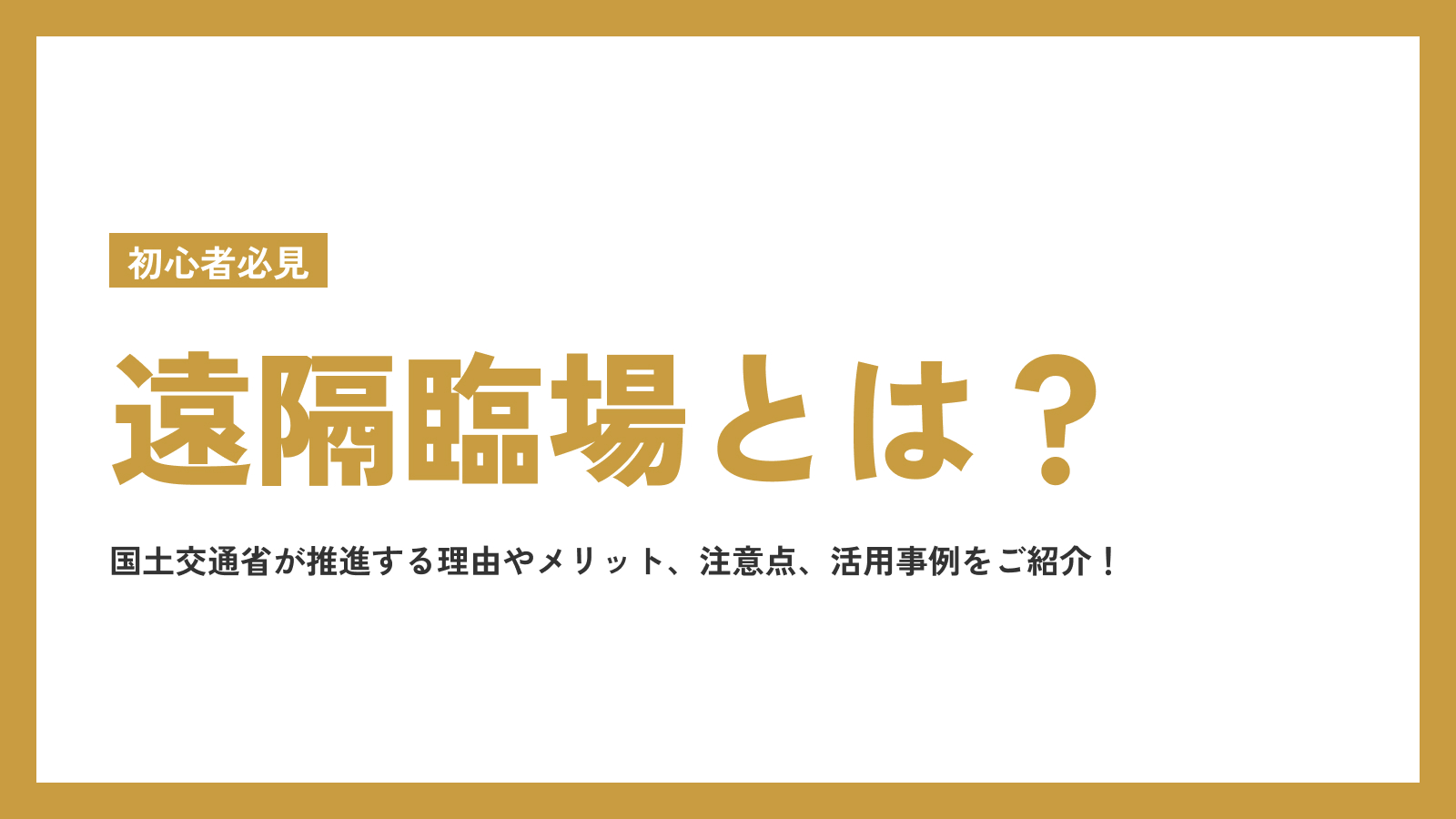
建築や土木業において、現場に行かなくとも臨場できる「遠隔臨場」をご存知でしょうか?
国土交通省も推奨しており、現場監督などの仕事をしている方からは、とくに注目されている仕組みです。
この記事では遠隔臨場とは何か、メリットや注意点、活用事例などをまとめてご紹介します。
遠隔臨場にご興味のある方はぜひ参考にしてください。
目次
遠隔臨場とは?
遠隔臨場とは、建設現場などでウェアラブルカメラやネットワークカメラを使って、現場に行かなくても離れた場所から確認作業や立ち会いを行うことです。
国土交通省が令和2年度から試行してきた取り組みで、令和4年度から本実施に移行しました。
遠隔臨場を実施するには、国土交通省が定めた試行要領に従って、機材やシステムの仕様や費用負担などの条件を満たす必要があります。
国土交通省が遠隔臨場を推進する2つの理由
国土交通省が遠隔臨場を推進する理由は主に2つあります。
1.高齢化に伴う労働人口の減少
日本の人口は2018年にピークを迎えて以降、減少傾向にあります。建設業界でも高齢化が進んでいるため、若年層就業者の不足は深刻な状況です。
必要技術の習得も含め、育成にも時間がかかる課題も抱えている中、遠隔臨場の仕組みが注目されています。
遠隔臨場を取り入れることで、従来現場臨場にかかっていた時間を他の仕事にあてられるようになるため、全体の業務効率化が図れ、結果手に必要人員の削減にもつながります。
2.感染症拡大の防止
新型コロナウイルス感染症の拡大は、建設業界にも大きな影響を与えました。建設現場では、多くの人が密集して作業することが多く、感染リスクが高いと考えられます。また、感染者が発生した場合、現場の停止や延期などの深刻な経済的損失が発生するかもしれません。
遠隔臨場を利用すれば、現場に出向く必要がなくなり、人と人との接触を減らせます。感染者が発生した場合でも、現場の作業を継続できます。
遠隔臨場の導入状況
国土交通省が2023年に都道府県47団体、政令指定都市20団体に遠隔臨場の導入について調査した結果、66団体で何らかの取り組みが実施されていることがわかりました。
具体的には、58団体では国土交通省が推奨している「段階確認」「材料確認」「立会」の実施が確認されています。さらに、残りの団体ではこれら3つの一部ないし3つ以外の内容での実施が確認されており、すでに多くの団体で遠隔臨場が導入されていることがわかります。
なお、2022年度から原則すべての直轄土木工事では、「段階確認」「材料確認」「立会」での遠隔臨場の適用が必要です。
遠隔臨場を導入する5つのメリット
遠隔臨場を、導入するメリットについて紹介します。
1.人手不足の解消につながる
遠隔臨場では、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを使って、離れた場所から確認作業や立ち会いを行います。監督や検査などの技術職は、複数の現場を効率的に管理することが可能です。
これにより、現場の監督者などの人員を減らせるため、人手不足の解消につながる効果が期待されています。
2.安全性が向上する
建設現場は、事故やトラブルが発生しやすい危険な環境です。遠隔臨場を取り入れることで、非接触・リモートで確認作業や立ち会いを行えるため、安全性が向上します。
また、安全性確保のため、専門家のアドバイスを遠隔から受けながら作業を進めることも可能になります。
3.リアルタイムの映像を確認できる
建設現場では、現場の状況や進捗状況を把握することが重要です。遠隔臨場は、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを使って、現場のリアルタイムの映像を確認できます。
また、映像を録画して保存することが可能となるため、現場管理における正確な状況報告が実現します。進捗に遅れが出た場合のスケジュール調整ミーティングにも使えるなど、メリットは多いです
4.移動時間の削減につながる
建設現場は地方や山間部などの過疎地にあることも多く、移動の時間が負担になることもあります。そのような時、現場に行かなくても離れた場所から確認作業や立ち会いを行う遠隔臨場はメリットが大きいでしょう。
また、移動の削減はコスト削減にもつながるといった、副次的なメリットも受けられます。
5.人材育成の効率化が図れる
建設業界では、若手や未経験者の育成が重要です。しかし現場での教育や指導は、先輩や専門家の負担が大きくなります。遠隔臨場は、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを使って、遠隔地から先輩や専門家の指導を受けられるのです。
また、先輩や専門家は複数の現場で教育や指導を行えるため、人材育成の効率化が図れます。
遠隔臨場を導入する際の注意点は4つ
遠隔臨場を導入する際には、注意することがあります。
1.通信環境の確保が必要になる
遠隔臨場は、ウェアラブルカメラやネットワークカメラを使って、現場の映像や音声を遠隔地に送信することで行います。そのため、安定した通信環境が必要です。
しかし、建設現場は地方や山間部などの過疎地に多くあり、通信環境が整っていない場合があります。また、現場の状況によっては、電波の干渉や遮蔽などで通信が途切れるかもしれません。
通信環境が悪いと、映像や音声が途切れたり、画質や音質が低下することがあります。これは、確認作業や立ち会いの精度や効率を低下させるだけでなく、安全性にも影響を与える可能性があります。
遠隔臨場を導入する際は、事前に現場の通信環境を調査し、必要に応じて通信機器や回線の強化を行うことが重要です。
2.機器を扱うための技術者が必要になる
遠隔臨場は、ウェアラブルカメラやネットワークカメラなどの機器を使って行います。そのため、機器の設置や操作、保守や管理などを行うための技術者が必要です。
しかし、現場で働く作業員は、機器の扱いに慣れていないかもしれません。機器を扱えないと、遠隔臨場の効果を発揮できないだけでなく、機器の故障やトラブルの原因にもなります。
遠隔臨場を導入する際は、機器の取り扱い方法や注意点を十分に教育し、技術者の育成や確保を行うことが重要です。
3.プライバシー侵害になる場合がある
遠隔臨場は、ウェアラブルカメラやネットワークカメラで現場の映像や音声を撮影するため、映像や音声に個人情報や秘密情報が含まれる可能性があります。
たとえば、作業員の顔や名前、現場周辺の住所や施設名、現場内の書類やパソコン画面などが映像や音声に映り込むかもしれません。
これらの情報が第三者に漏洩したり悪用されたりすると、プライバシー侵害や損害賠償などのトラブルに発展する可能性があります。
遠隔臨場を導入する際は、映像や音声の送信先や保存先、閲覧者や利用者などを明確にし、適切なセキュリティ対策を行うことが重要です。また、映像や音声に含まれる個人情報や秘密情報を適切に管理し、必要に応じてマスキングや削除などを行うことも必要です。
4.機器の導入にコストがかかる
遠隔臨場に用いるウェアラブルカメラやネットワークカメラなどの機器導入には、購入やレンタル、設置や保守などのコストがかかります。
機器の種類や性能、数量や期間などによって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度の費用が必要となります。また、必要に応じて、通信環境の整備や技術者の育成なども必要となるため、機器の導入以外にもコストが発生する可能性を考慮しておく必要があるでしょう。
遠隔臨場を導入する際は、コストと効果のバランスを考えることが重要です。また、国土交通省などから補助金や助成金の支援制度を受けることも検討するとよいでしょう。
遠隔臨場の活用事例3選
実際に遠隔臨場を活用した事例について紹介します
事例1.松本市上下水道局
参考元:松本市上下水道局HPより
松本市上下水道局では、DXやIoT(Internet of Things)の推進による業務効率化の一環として「LTE対応ポータブルカメラ」を試験導入しています。
- 配水管の仕切弁開閉作業を三脚に固定したLTEカメラで撮影し、庁舎から作業者にアドバイスをしたり、映像を教育指導に使ったりする
- 補修工事のため空になった減圧槽の中を胸につけたLTEカメラで撮影し、薄暗い槽内でもLEDライト機能を使って明るく撮影する
- 作業の振り返りとして自分が行った作業の様子の映像を確認する
- 水道管の更新工事や施設の耐震化工事などで現場と庁舎をつないで設計変更する
- 管理監督や検査記録として映像で記録する
松本市上下水道局では、今後もLTEカメラを使って現場管理や教育指導などに活用していく予定です。
事例2.関東地方整備局
参考元:関東地方整備局HPより
関東地方整備局では、令和2年度から遠隔臨場の試行に取り組んでおり、令和4年度からはすべての工事を対象に本格的な実施に移行しています。遠隔臨場の実施にあたっては、発注者指定型という方式を採用しています。
発注者指定型とは、発注者が遠隔臨場にかかる費用を全額負担し、受注者が通信機器やソフトウェアを準備する方式です。
遠隔臨場の実施により、以下のような効果が確認されています。
- 現場への移動時間の短縮:令和3年度は約1,000時間の移動時間が削減
- 立会に伴う受注者の待ち時間の短縮:令和3年度は約1,200時間の待ち時間が削減
- コロナ禍での感染防止対策:現場での人数や接触時間の削減
- 遠隔地からの専門家の参加:専門家や技術者が現場に直接赴く必要がなくなった
関東地方整備局では、遠隔臨場の効果や課題を検証しつつ、インフラ分野のDXを推進していく予定です。
事例3.りんかい日産建設株式会社
参考元:りんかい日産建設HPより
りんかい日産建設株式会社は、国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」に登録されている「V-CUBE
コラボレーション」という遠隔作業支援ソリューションを導入しました。
音声だけでスマートグラスの起動から写真撮影、監督官への画像送信まで行えるので、作業者は両手が空いた状態で遠隔臨場を行えます。その結果、監督官の移動コストは5分の1に減少し、現場臨場の回数も5分の1程度に減少しました。
遠隔臨場でよくある3つの質問
遠隔臨場でよくある質問について、紹介します。
質問①遠隔臨場で利用するカメラの種類は?
遠隔臨場で利用するカメラの種類は、以下のように分類できます。
- ウェアラブルカメラ:ヘルメットや頭部・身体に装着できる小型のカメラ
- スマートグラス:眼鏡型のデバイスで、カメラやディスプレイ、マイクなどが内蔵されている
- スマートフォン・タブレット:手持ちのモバイル端末で、カメラや通話機能を使って映像や音声を送受信できる
- 赤外線カメラ:赤外線を使って、暗闇や煙などの中でも映像を撮影できる
遠隔臨場に使われるカメラは画質や通信速度、操作性などの要件を満たす必要があります。
質問②国土交通省が手掛ける「i-Construction」とは?
i-Constructionとは、国土交通省が進めているプロジェクトのうちの1つです。建設現場における生産性向上と労働環境改善を目指しています。具体的には、以下3つの柱があります。
- ICT技術の全面的な活用(ICT土木):測量・設計・施工・検査・維持管理などのプロセスにICT技術を導入し、効率化や品質向上を図る
- 規格の標準化(コンクリート工):コンクリート工の工法や鉄筋のプレハブ化、部材サイズの標準化などを行い、プロセス全体の効率化やコスト削減を図る
- スマートフォン・タブレット:手持ちのモバイル端末で、カメラや通話機能を使って映像や音声を送受信できる
- 施工時期の標準化:年度末に工期が集中することを防ぎ、発注者の計画性向上や労働者の収入や休暇の安定化を図る
質問③遠隔臨場適用の範囲は?
遠隔臨場適用の範囲は「段階確認」「材料確認」と「立会」に適用すると定められています。
- 「段階確認」:工事進捗に応じて発注者が施工内容や品質を確認すること
- 「材料確認」:工事に使用する材料が規格や仕様に合致しているかを確認すること
- 「立会」:発注者が施工者と共に工事現場で作業内容や方法を確認すること
これらの確認項目において、遠隔臨場の適用性(目安)を公表しています。
まとめ
遠隔臨場とは、建設現場の映像や音声をウェアラブルカメラやネットワークカメラなどで遠隔地に送信し、Webシステムなどで確認作業や立会いを行うことです。
国土交通省は令和4年度から遠隔臨場を本格的に実施し、その普及と発展を図っています。
遠隔臨場を導入することで、人手不足の解消や安全性の向上など、さまざまなメリットがあります。ただ、運用を確実なものにするためには、通信環境の確立などの注意が必要です。
遠隔臨場技術は、災害対応やインフラ整備、教育・研修などの分野で活用されており、今後もさらに発展していくと考えられています。
RICOHのRICOH Remote Fieldは、360°映像の双方向型ライブ配信システムにより、遠隔地から現場の状況確認が可能になり、遠隔指導による生産性向上を実現できます。⇒RICOH Remote Field
お見積り・お問い合わせ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。