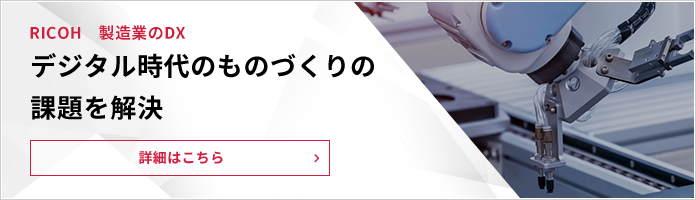RFID技術の普及に伴い、多くの企業がRFIDタグの導入を検討しています。しかし、導入の際に最も気になるのが「価格」という観点ではないでしょうか。
本記事では、RFIDタグの種類別の価格帯や、導入時のコスト構造について詳しく解説していきます。特に、近年の技術革新による価格動向についても焦点を当てていきましょう。
RFIDタグとは

RFIDとは「Radio Frequency Identification(無線周波識別)」の略称で、電波を用いて非接触で情報をやり取りする技術のことです。小型のICチップとアンテナを組み込んだRFIDタグは、バーコードとは異なり、目視できる印刷物を必要とせず、電波を介してデータを送受信します。
また、一度に複数のタグを読み取れる上、タグとリーダの間に障害物があっても認識が可能という特徴があります。製品の在庫管理や物流トラッキング、入退室管理など、私たちの生活のさまざまな場面で活用されており、IoT(Inernet of Things)時代の重要なインフラ技術として注目を集めています。
関連記事:RFIDタグで在庫管理を効率化するには?仕組みや使い方、コストについて説明
RFIDタグの導入にかかる費用内訳

RFIDタグの導入費用は、導入規模やシステムの複雑さによって大きく異なります。一般的に、以下の項目が費用に含まれます。また、導入にかかる初期費用に加えてランニングコストもかかってくる点は留意しておきましょう。
RFIDタグ本体の費用
データを記録するICチップとアンテナを内蔵した個々のタグの購入費用です。用途や性能によって単価は大きく異なり、数円から数百円まで幅があります。導入数量によって価格は変動し、大量購入での単価引き下げが可能です。
リーダ/ライタの費用
RFIDタグのデータを読み取り・書き込みを行う機器の購入費用です。据え置き型、ハンディ型、ゲート型など、形状や用途によって数万円から数十万円の範囲で価格が変動します。読み取り距離や同時読取数などの性能によっても価格は異なります。(2024年12月現在)
アンテナの費用
リーダ/ライタに接続して電波を送受信するためのアンテナの購入費用です。設置場所の環境や必要な読取範囲によって選定が必要で、数万円から十数万円程度します。複数設置が必要な場合は、その分コストが上がります。(2024年12月現在)
ソフトウェアの費用
RFIDシステムを制御し、データを管理・分析するためのソフトウェア費用です。既製品の購入やカスタマイズ開発の費用が含まれ、数十万円から数百万円規模となります。保守料や使用料が別途必要な場合もあります。(2024年12月現在)
その他の費用
システム導入時の設置工事費、運用テスト費用、従業員教育費用、保守メンテナンス費用などが含まれます。また、既存システムとの連携のための追加開発費用や、電波環境調査費用なども考慮が必要です。
RFIDタグの価格相場

RFIDタグの現在の価格相場は10~15円程度とされています。(2024年12月現在)
ただし、印刷技術を用いることで、将来的にはRFIDタグの単価が1円未満にまで引き下げられる可能性があります。これにより、使い捨てが可能な用途への普及が進むと予想されています。
【最新】RFIDタグの価格推移

RFIDタグの価格は過去10〜15年間で大きく変動しており、以前は1枚数十円していたものが、現在では一般的なタグで1枚約10円程度まで下落しています。特に発注数量が1億枚を超える大口注文の場合、1枚5円程度まで価格を抑えることが可能です。(2024年12月現在)
ただし、原材料費の観点から、現状では1枚2円が実質的な下限価格とされています。また、金属対応など特殊な用途向けのタグは、従来は非常に高価でしたが、技術革新により100円程度まで価格が低下してきました。
経済産業省が推進する「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」の実現に向けて、2025年頃までにさらなる価格低下が期待されていますが、1円以下という目標達成には、ICチップの小型化などの技術的なブレークスルーが必要とされています。
RFIDタグの選び方のポイント

RFIDタグの選び方は、導入目的や環境によって異なります。最適なタグを選ぶために、以下のポイントを考慮しましょう。
使用環境と用途を明確にする
RFIDタグを選ぶ際には、まず設置場所の環境条件を詳細に把握することが重要です。屋内か屋外か、温度や湿度の変化、直射日光の有無、水や薬品との接触可能性など、タグが晒される環境要因を確認する必要があります。
次に、対象物の材質や形状も重要な選定基準となります。特に金属や液体の近くで使用する場合は、電波の干渉や減衰を考慮した専用タグの選択が必須です。
また、読み取り距離の要件に応じて、アンテナの性能や設置方法を検討する必要があります。例えば、ゲート式の自動読み取りを行う場合と、ハンディリーダーで近接して読み取る場合では、最適なタグの種類が異なってきます。
これらの要件を総合的に判断し、用途に最適なタグを選定することで、確実な運用が可能となります。
タグの種類を選択する
RFIDタグの選択では、電源方式の違いによる3種類のタグから用途に応じて最適なものを選ぶことが必要です。最も一般的なパッシブタグは、電池を内蔵せず、リーダからの電波で駆動するため、小型・軽量で低コストという特徴があります。
一方、アクティブタグは内蔵電池で動作し、長距離の通信や複雑なデータ処理が可能ですが、価格が高く、電池交換が必要という課題があります。半パッシブタグは、内蔵電池をセンサーなどの動作にのみ使用し、通信時はリーダからの電波を利用するハイブリッド型で、温度管理など特殊用途に適しています。
導入目的、コスト、使用環境、通信距離、データ量などを総合的に考慮して、最適なタグを選択することが重要です。
周波数を選択する
RFIDタグの周波数選択は、用途や環境に応じて慎重に検討する必要があります。最も一般的なHF帯(13.56MHz)は、読み取り距離が数十センチメートルと比較的短いものの、金属や水分の影響を受けにくく、安定した読み取りが可能です。
これに対しUHF帯(860-960MHz)は、数メートルの読み取り距離を実現でき、複数タグの同時読み取りに優れていますが、金属や水分の影響を受けやすい特徴があります。
その他、LF帯(125-134kHz)は読み取り距離が極めて短いものの、金属環境での使用に適しており、マイクロ波帯(2.45GHz)は長距離通信が可能ですが、コストが高くなる傾向です。用途に応じて、これらの特性を考慮したうえで選択しましょう。
メモリ容量を選択する
RFIDタグのメモリ容量を選択する際は、記録する情報量と書き込み回数の2つの要素を慎重に検討しなければなりません。情報量については、製品コードや製造日などの基本情報のみを記録する場合は数バイト程度で十分ですが、詳細な製品情報や履歴データを管理する場合は、数キロバイト以上の容量が必要になります。
一方、書き込み回数については、一度書き込んだ情報を変更しない用途であれば書き換え不可のROMタイプで十分ですが、在庫状況や物流履歴など情報を随時更新する必要がある場合は、数万回以上の書き換えが可能なEEPROMやFeRAMタイプを選択することが望ましいでしょう。
ただし、メモリ容量と書き換え回数が増えるほどタグの単価も上昇するため、実際の運用に必要最小限の仕様を選定することがコスト最適化のポイントとなります。
RFIDタグを選ぶ際の注意点

RFIDタグを選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要があります。導入を成功させるために、以下の点に注意して最適なタグを選んでください。
金属への影響
RFIDタグは金属の影響を強く受けるため、金属製品への取り付けには特別な配慮が必要です。一般的なRFIDタグを金属に直接貼り付けると、金属が電波を反射・吸収してしまい、正常な通信ができなくなる可能性が高くなります。
そのため、金属製品に取り付ける場合は、専用の金属対応タグを選択する必要があります。これらの特殊タグは、金属の影響を軽減する特殊な素材や構造を採用しており、通常のタグと比べて価格は高くなりますが、近年の技術革新により1枚100円程度まで価格が下がってきています。
また、金属対応タグを選ぶ際は、対象物の材質や形状、使用環境に応じて、通信距離や耐久性などの仕様も併せて検討することが重要です。
電波干渉
RFIDタグを導入する際は、周辺環境における電波干渉の影響を十分に考慮する必要があります。特に工場や物流現場では、無線LANや生産設備、フォークリフトなど様々な機器から発せられる電波が存在するため、これらとRFIDの電波が干渉し合うことで、読み取り精度の低下や誤作動を引き起こす可能性があります。
そのため、導入前に電波環境の事前調査を行い、使用する周波数帯の選定や、アンテナの設置位置・向きの最適化、必要に応じて電波遮蔽対策を講じることが重要です。
また、複数のRFIDリーダを近接して設置する場合は、リーダ間の相互干渉を防ぐため、適切な設置間隔や電波出力の調整が必要となります。
リーダ/ライタとの互換性
RFIDタグを導入する際、使用予定のリーダ/ライタとの互換性確認は極めて重要です。互換性の問題で読み取りができない、あるいは性能が著しく低下するケースを避けるため、まず周波数帯(HF帯・UHF帯など)が一致していることを確認する必要があります。
また、リーダ/ライタが対応している通信プロトコルとタグの仕様が合致しているかも重要なポイントです。特に既存のリーダ/ライタを使用する場合は、事前にタグメーカーに互換性の確認を行うことが推奨されます。
さらに、実際の使用環境での読み取りテストを行い、期待通りの性能が得られるか検証することで、導入後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
RFIDタグの価格は技術革新と需要の拡大により、年々低下傾向にあり、導入のハードルは確実に下がってきています。しかし、成功的な導入のためには、単にタグの価格だけでなく、使用環境や用途に応じた適切な製品選定、金属や電波干渉への対策、リーダ/ライタとの互換性など、様々な要素を総合的に検討する必要があります。
2025年に向けて更なる価格低下と技術革新が期待される中、企業は自社の業務効率化やコスト削減のために、RFIDタグの導入を前向きに検討する良いタイミングと言えるでしょう。ただし、導入に際しては、事前の十分な検証と段階的な展開を心がけることが、成功への近道となります。
リコーはこれらのRFIDソリューションの提供を通じて、製造や物流、販売業務での入出庫管理、工程管理、資産・備品管理におけるさまざまな課題の解決を支援します。